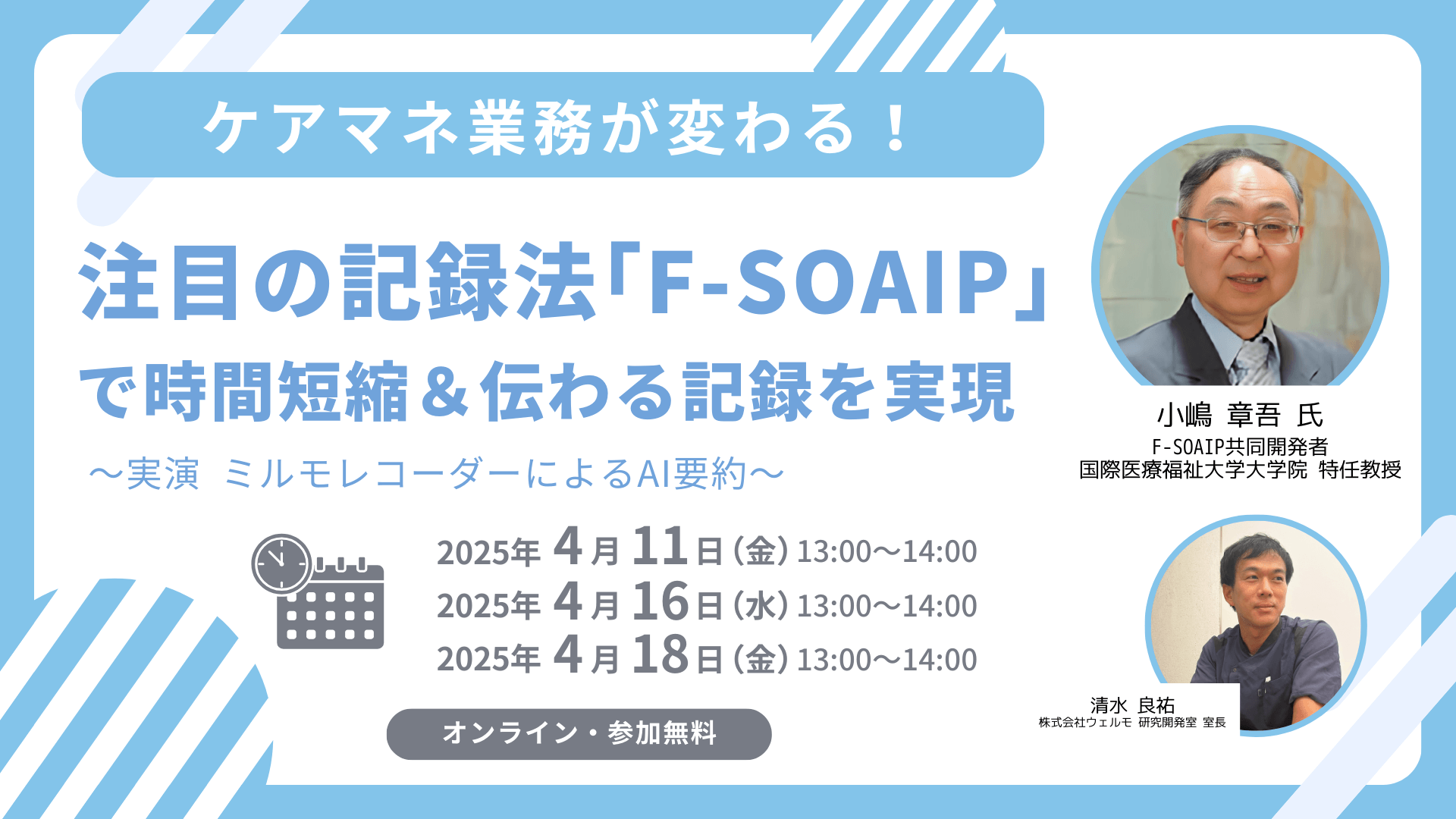訪問介護と通所介護、人材の行き来を柔軟に 厚労省 地方を中心に具体化検討


厚生労働省は7日、2040年を見据えて介護サービス提供体制のあり方を議論する検討会を開き、今後の取り組みの方向性を描いた「中間とりまとめ(案)」を提示した。【Joint編集部】
介護ニーズが縮小していく中山間・人口減少地域を中心とした施策の中に、訪問介護と通所介護の運営基準の弾力化を盛り込んだ。サービス間の連携を深めるほか、双方の人材が柔軟に行き来できる仕組みの整備を図る構想を掲げた。
サービスをより効率的に提供できる環境を生み出す狙い。厚労省は「中間とりまとめ(案)」に、「介護人材や専門職の確保が困難な中、様々な人員配置基準について弾力化していくことが考えられる」と記した。
今後、審議会で具体的な議論を進めていく方針。検討会はこうした内容を大筋で了承した。
厚労省は2024年度の介護報酬改定をめぐる議論のプロセスで、訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型サービスを新設する案を俎上に載せ、「さらに検討を深める」としていた経緯がある。
今回の検討会の終了後、厚労省の関係者は「中山間・人口減少地域の方がより必要性が高い。新しい複合型サービスを作るのか、お互いの基準をもう少し整理するのか、その辺りはよく詰めていかないといけない」と話した。
◆ 訪問介護は包括評価の検討も
厚労省はこのほか「中間とりまとめ(案)」に、中山間・人口減少地域の施策として訪問介護の出来高払いの見直しも盛り込んだ。
「訪問回数を単位として評価しているため、利用者の突然のキャンセルや利用者宅間の移動にかかる負担が大きい。こうした状況に対応する方策を検討することが必要」と説明。「全体の報酬体系との整合性や自己負担の公平性などにも配慮しながら、介護報酬の中でこれに対応できる包括的な評価の仕組みを設けることも検討の方向性として考えられる」と記した。