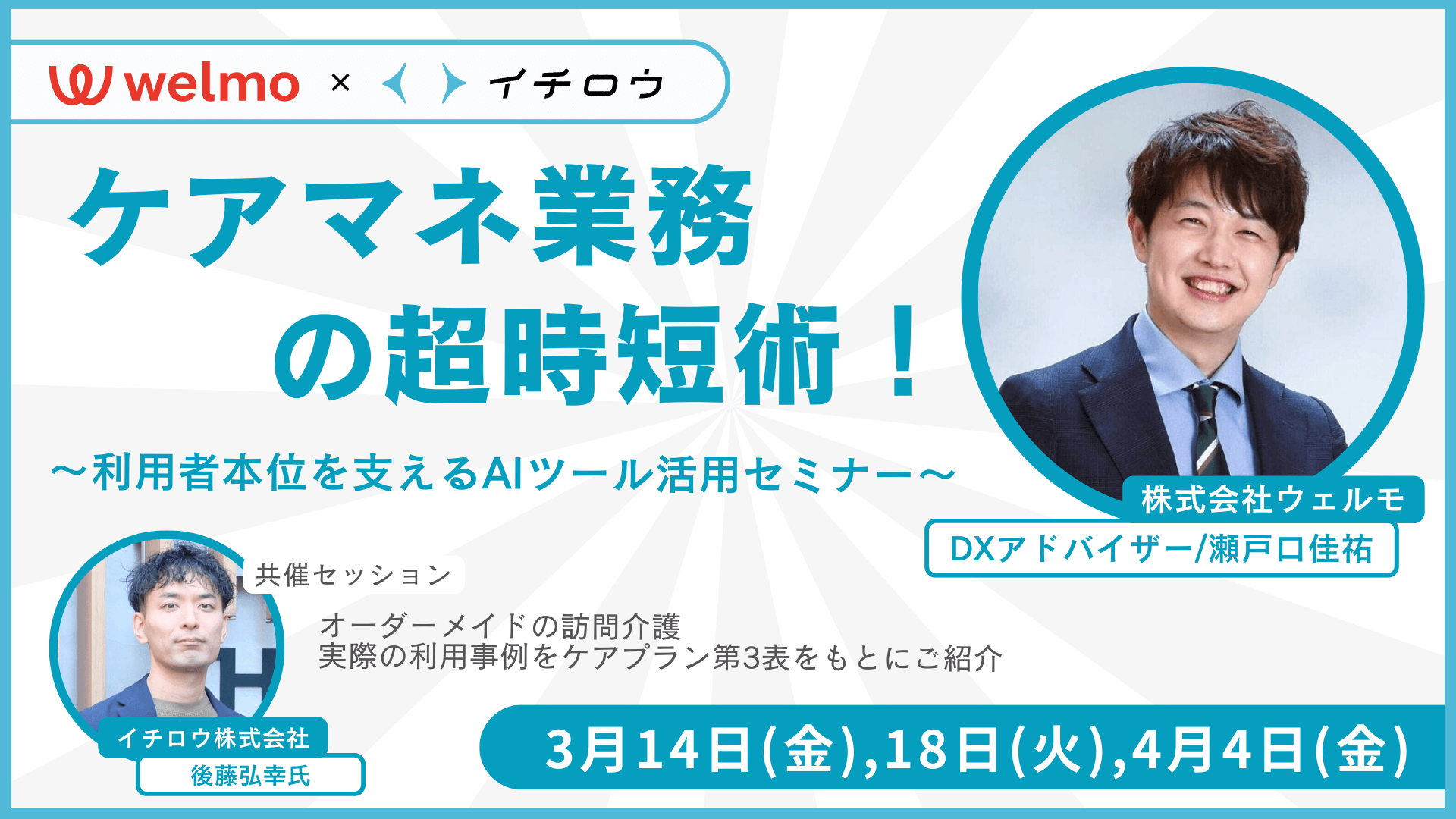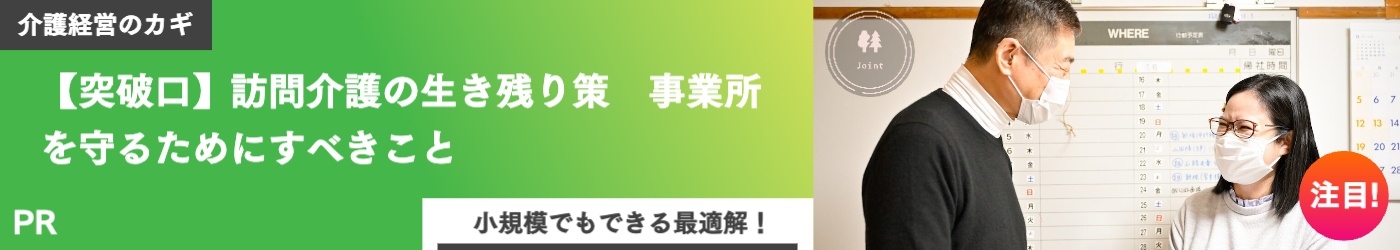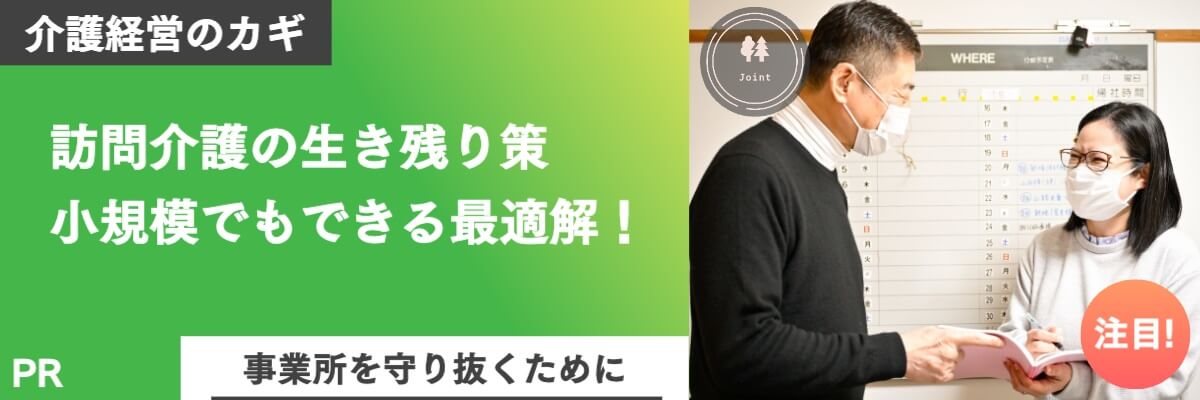【青柳直樹】「それ、誰の仕事?」で立ちすくむ現場 介護と看護の“もやもや”を超えて負担を減らすために


介護の現場では、職種ごとの役割分担が曖昧なままになっているケースが少なくありません。「このケアは介護職がやってもいいの?」「施設によってルールが違うのはなぜ?」といった声が、今も多く寄せられています。【青柳直樹】
介護職と看護職の仕事の境界線が明確でない状態が続けば、どちらかの負担が過度に大きくなり、結果として現場全体の生産性が低下する原因にもなりかねません。特に、医療的ケアの可否が判断しにくいグレーゾーンの存在は、混乱の火種となってしまいます。

青柳直樹|医師。2017年にドクターメイト株式会社を創設。日本ケアテック協会の理事も務める。介護施設が直面する医療課題に対応すべく、オンラインの医療相談や夜間のオンコール代行などのサービスを展開中。介護職の負担を減らすこと、利用者の不要な重症化、入院を減らすことなどに注力している。
◆ できるのに任せられない理由
例えば、爪切りや耳垢の除去といった行為は、本来であれば介護職が実施してもよいとされています(*)。しかし現場では、「万一トラブルがあったら」「誰が責任を取るのか」といった不安から、看護職が常に引き受けてしまうことも少なくありません。
* 爪切りや耳垢の除去の全てではない。例えば爪切りの場合、爪そのものに異常がなく、周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病などの疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に認められる。耳垢の除去にも一定の条件がある。
看護職側にとっては、どこまでなら任せていいかを判断すること自体が負担です。「自分でやった方が早い」という考えに傾きやすく、結果的に業務の偏りや疲弊につながってしまいます。
また、職場ごとの対応のばらつきが、職員の不安感や不満を生む要因にもなっています。「前の職場ではやっていたのに、ここではNGと言われた」「やりたいケアがあるのに許されない」。こうしたミスマッチは離職やモチベーションの低下にも直結します。
◆ グレーゾーンを「施設基準」で埋める
現行の法制度に目を向けると、医療行為の範囲について国から一定の指針が出されています。医療行為でないものは介護職が実施可能ですし、一定の条件付きで許されている行為もあります。
しかし、その「一定の条件」があいまいで、現場の判断に委ねられている部分も多くあります。糖尿病のある利用者の爪切り、外耳に疾患がある人の耳掃除など、程度や状態によって判断が分かれるケアは特に慎重さが求められるでしょう。
こうした“グレーゾーン”への対応として、施設ごとにルールや基準を設け、職員間で合意を形成しておくことが非常に重要です。国が明確に定めていないからこそ、「やらない」ではなく、「この範囲まではやってよい」と決めておく。それが、トラブルを未然に防ぐ最良の手段となります。
もちろん、施設側で全て勝手に判断していいというわけではありません。分からないところは行政にも相談しつつ、あくまでもルールの範囲内で適切に線を引いてください。重要なのは曖昧にしないこと、一部の職員にしわ寄せがいくのを避けることで、独断で決めるのは避けましょう。
◆ タスクシフトは「モチベーションシフト」
今後、85歳以上の高齢者の人口が急増し、介護現場の医療ニーズはますます高まっていきます。そうした時代に求められるのは、職種間での役割分担を明確にし、それぞれが専門性を発揮しながら協力する体制です。
単に業務の移管という意味での「タスクシフト」ではありません。むしろ、介護職が「自分に任されている」「信頼されている」と実感できるような、モチベーションの転換が重要です。
実際、これまで看護職が担っていた業務の一部を、介護職が自信を持って引き受けられるようになれば、現場の生産性は確実に向上します。属人化を防ぎ、チーム全体でケアの質を高めていくためにも、タスクシフトは避けて通れないテーマです。曖昧さを放置しない、それが未来の準備になるはずです。
国の制度がすべてのケースをカバーするのは難しく、現場での判断が求められる状況は今後も続くでしょう。だからこそ、「これはうちの施設ではどう扱うのか?」を話し合い、共有する機会を意識的に設けていくことが必要です。
グレーな部分に対して単に消極的になるのではなく、ルールに則って「私たちはこの範囲まではやる」と線を引くこと。そうした主体的な姿勢が、介護現場における自律性と持続性を生み出します。
介護職と看護職が互いの領域を正しく理解し、共に支え合える現場へ。その第一歩は、役割分担の見直しと明文化から始まります。未来の人手不足を見据えて、今できることを、現場から積み重ねていきたいものです。