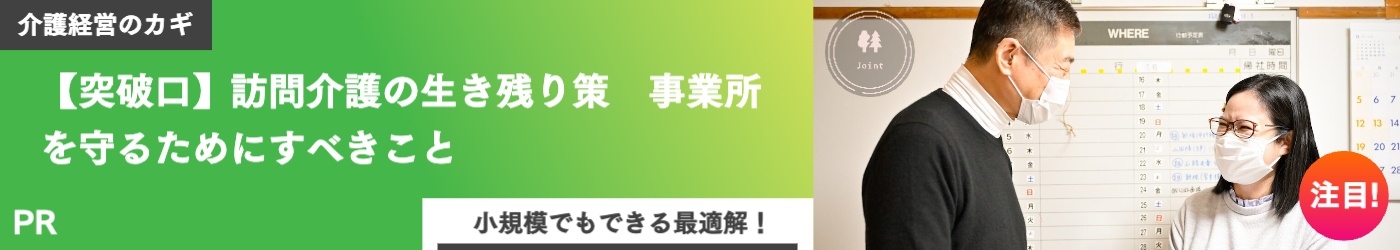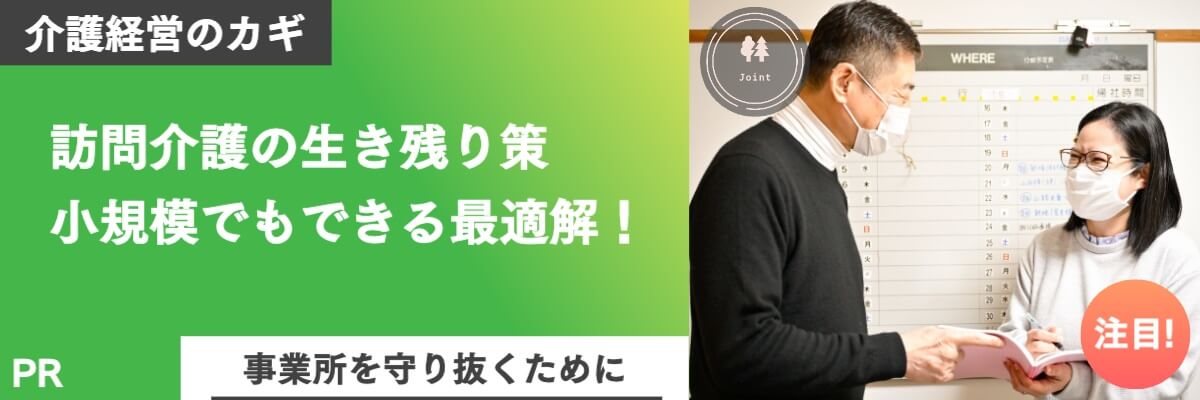【片岡眞一郎】介護テクノロジー重点分野が拡大 在宅での活用も強化 現場への影響大


補助金の対象機器が広がる可能性もある。事業所・施設への影響は小さくなさそうだ。【片岡眞一郎】
介護現場の生産性向上の取り組みとして、介護ロボットやICTなどのテクノロジーの活用が注目されているが、こういった革新的な機器の開発促進・普及を目指す国の考え方が一部変わる。今年4月から「ロボット技術の介護利用における重点分野」が改訂され、名称も「介護テクノロジー利用の重点分野」に変更される。
昨今のICT・IoT技術を用いたデータの利活用が進む状況、介護現場における新たな社会課題を踏まえての改訂となる。
今回の改訂では、以下の5つの重点分野が「基本的な考え方」とされた。自立支援・社会参加などケアの質の向上につながるテクノロジーに重点を置くこと、在宅での活用に重点を置くことが示されている。詳細は以下の通りだ。
◯ 介護テクノロジーの活用により、介護サービスの質を確保するとともに、職員の負担軽減に資する生産性向上の取り組みを推進し、魅力ある職場環境づくりを目指す。
◯ 介護テクノロジーの活用により、自立支援・社会参加などによる高齢者らの本人の生活の質の維持・向上を実現することを目指す。
◯ ICTやIoT技術、AI予測エンジン、データ利活用サービスといったデジタル技術の進展動向を踏まえる。
◯ 入所系サービスなど限られたサービス類型での利活用だけでなく、在宅など様々な環境での利活用が必要であることを踏まえる。
◯ 技術オリエンテッドではなく、介護現場のニーズが真に反映され、誰もが利用したいと感じられる介護テクノロジーの開発などを推進する。
◆ 3分野が新設
具体的な変更点としては、現在の重点分野である6分野(*)13項目から新たに3分野が追加され、合計9分野16項目となることがあげられる。また、既存の分野・項目の定義文についても一部見直される。
* 移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション・入浴支援、介護業務支援
新設される3分野は、「機能訓練支援」「食事・栄養管理支援」「認知症生活支援・認知症ケア支援」となる。
「機能訓練支援」のテクノロジーは、「介護職らが行う身体機能や生活機能の訓練における各業務(アセスメント・計画作成・訓練実施)を支援する機器・システム」と定義されている。
身体機能を簡便に評価できるセンサーや、個々に応じた訓練内容を提案できるAIエンジンの開発により、リハビリテーション専門職以外でも個別的な機能訓練が行えるよう支援する機器・システムの開発が進んでいることが影響している。高齢者の歩行状態をカメラで可視化するアプリや計画策定など、機能訓練を支援する機器・システムが対象となってくる。
「食事・栄養管理支援」は、「高齢者らの食事・栄養管理に関する周辺業務を支援する機器・システム」と定義されている。ICT技術の発展や画像認識AIの精度の向上により、利用者の口腔・嚥下機能を可視化すること、食事の摂取量・内容を推定することなどが、技術的に進んできたことも影響している。誤嚥を検知する機器・システム、食事量・栄養摂取状況を把握する機器・システムが対象となってくる。
「認知症生活支援・認知症ケア支援」は、「認知機能が低下した高齢者らの自立した日常生活または個別ケアを支援する機器・システム」と定義されている。この分野では、認知機能が低下した人の自立生活の促進、家族を含めた介護負担の軽減などが期待される。周辺症状を予測する機器、適切な援助をリコメンドできる機器など、認知症の人の生活を支援するために、ご本人や家族・介護従事者が使用する機器が対象となってくる。
◆ 問われる有効活用
また、今回の改訂では8項目の定義文について見直しがなされた。例えば入浴支援機器。従来は「ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器」だったが、今回の改訂で「入浴におけるケアや動作を支援する機器」となった。介護現場において、高齢者の清潔を保つことを目的とした機器の普及が進んでいることを踏まえた変更だ。
また、排泄支援(排泄予測・検知)機器について、従来は「ロボット技術を用いて排泄を予測し、的確なタイミングでトイレへ誘導する機器」だったが、今回の改訂で「排泄を予測または検知し、タイミングの把握やトイレへの誘導を支援する機器」となった。こちらも、排泄「後」の検知ができる機器の普及や、排泄時のアセスメントにおけるニーズを踏まえた変更となった。
重点分野の改訂は、開発企業はもちろんのこと、介護事業所にも大きな影響を与える。それは、導入に関する補助金の対象機器が変わる可能性があるということだ。補助金の対象機器に関しては、自治体・都道府県から発信されるが、新たに加わった3分野や定義文が見直されたことにより、対象機器が従来よりも拡充される可能性がある。
一方で、自治体・都道府県の財源は限られているため、今後は、介護テクノロジーがきちんと活用されるように、事前の計画や想定効果などが一層求められてくる。
2025年1月末時点で31の都道府県で生産性向上総合相談センターが設置されている。補助金の活用を検討している場合は、各センターが主催するセミナーや研修の確認などもあわせて、積極的に情報収集を進めていくことも重要になるだろう。