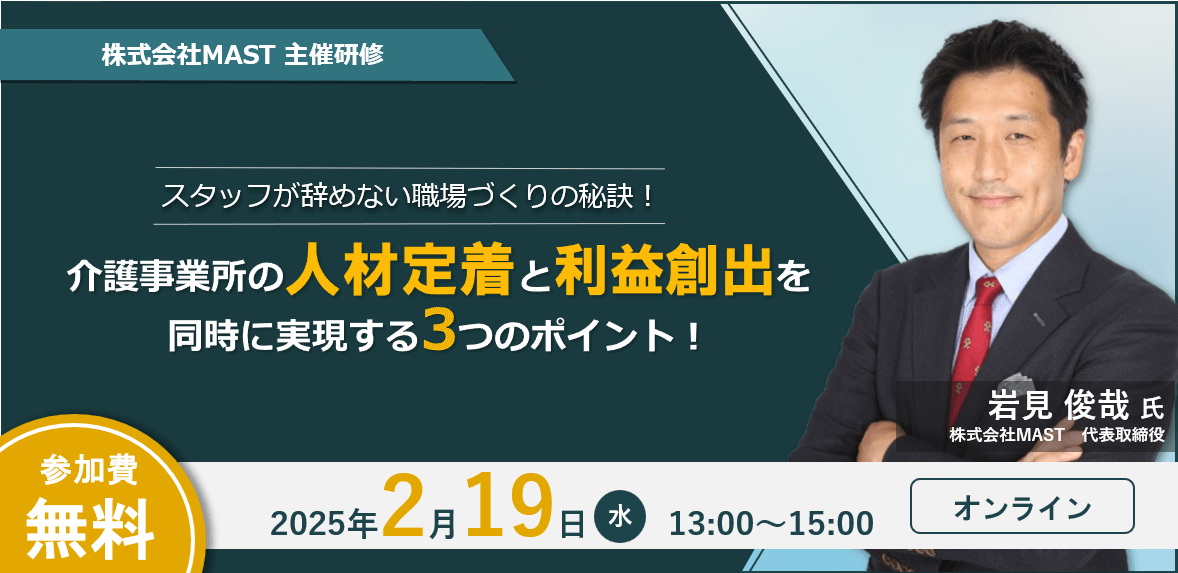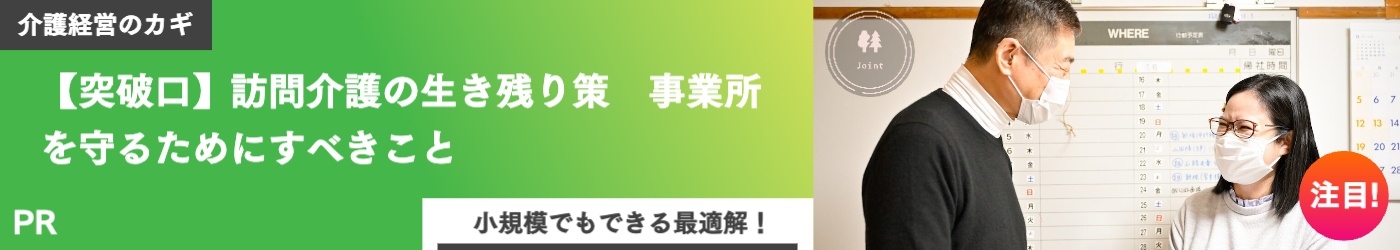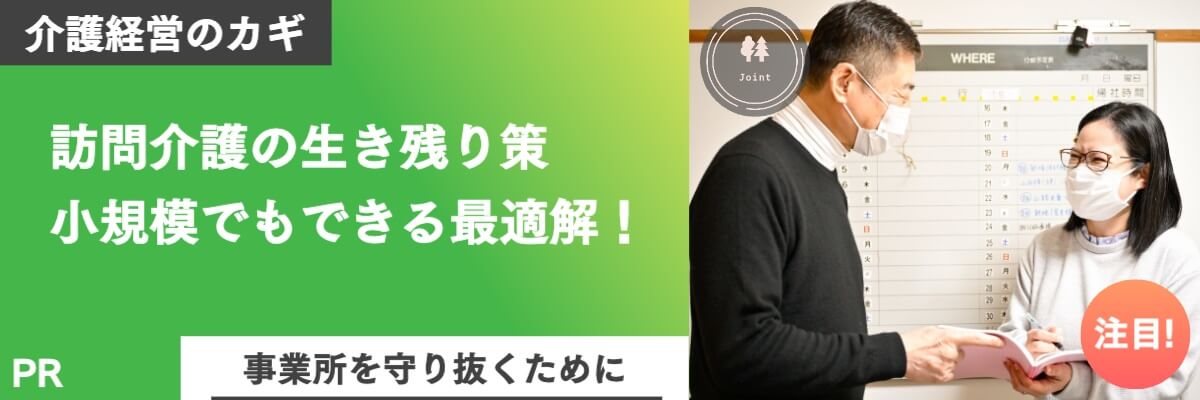前回の介護報酬改定が決着してから概ね1年が経ちましたが、訪問介護の基本報酬のマイナス改定については、今なお業界内外から厳しい評価の声があがっています。【天野尊明】
ここまでの状況になれば、少なくとも国民の実感から大きく外れたものであったことは明らかで、厚生労働省の失策だったと総括すべきでしょう。その後に火消しとして手当てした賃上げ策についても、処遇改善加算の算定促進を軸とした半端なものであって、患部に直接届くようには見えません。
◆ 単独か同一建物か
こうした状況の中で、1月30日に開かれた厚労省の専門家会議で、今年度の「介護事業経営概況調査」が審議されました。これは、「各サービスの施設・事業所の経営状況を把握し、次期制度改正・報酬改定に必要な基礎資料を得ること」を目的とする調査です。
厚労省は専門家会議で、今年度に行う同調査の方針として、「訪問系サービスについて、訪問先の状況、訪問に係る移動手段、移動時間を把握するための項目を追加する」との案を示しました。
ここで思い出されるのは、前述の訪問介護のマイナス改定が発表された直後の審議会です。民間介護事業推進委員会の稲葉雅之委員は、国の調査で訪問介護の収支差率が7.8%と高い結果になり、それがマイナス改定の理由になったことについて、次のように発言しました。
「これは同一建物における訪問介護が含まれている数字であり、同一建物におけるサービスを除いた訪問介護の収支差率は7.8%より大分低いはず。基本報酬を引き下げる対象として適当でない」
他の委員の方々も同様の指摘をしていたため、厚労省は「次期報酬改定に必要な基礎資料」として、その実態を把握しておきたいと考えたのでしょう。
ただし、これはあくまで業界側からの期待値を含めた見方です。同じデータを基に議論するとしても、「単独の訪問介護事業所は厳しい」というための根拠にするのか、「囲い込みは儲けている」というための根拠にするのかで、改定の方向性は大きく変わります。
もちろん、財務省的な感覚では後者になると思いますし、そもそも前者のような考えがあるのなら、あの局面でマイナス改定などしなかったでしょう。
少なくとも、訪問介護のサービス提供のありようを報酬改定の文脈で分析しようという以上は、そこに何らかのセグメントを設ける可能性が検討されるのでしょう。この調査の行方に対し、十分な注目と世論による後押しが必要であることは言うまでもありません。
◆ 生産性加算などにも変化の兆し
また、今回の専門家会議では同調査の見直しの項目として、「介護ロボットやICTなど介護テクノロジーについて、その導入状況を把握するための項目を追加するとともに、保守・点検などのランニングコストの金額を記載する欄を追加する」という案も示されました。
これも非常に興味深く、筆者も含めた業界関係者が異口同音に「介護テクノロジーについては導入だけでなく、更なる活用のための費用を支援することが必要」と求めてきたことが、施策に反映される方向であることが窺えます。
この調査の趣旨を踏まえれば、次期報酬改定における生産性向上関連の加算などの見直しをめぐり、要件や単価の根拠として「ランニングコスト」を見込んでいると考えられます。
ここについても、今の介護テクノロジーの導入・活用の状況を考えれば、平均値でなく中央値で評価する必要があることは言うまでもありません。調査の結果を待つだけでなく、実践者の側から有意な数字を積極的に発信していかなければ、形だけのものになる恐れがあるでしょう。
以前の当欄で筆者は、「今後の介護業界に求められるのは、出された結果に驚きながら不利な戦いに挑むことではありません。『予測される未来に備えること』です」と申しあげました。
次期報酬改定の議論が本格化する前に、我々にもできることがあります。それぞれの立場で、より良い未来のためにできるアクションを重ねていきましょう。