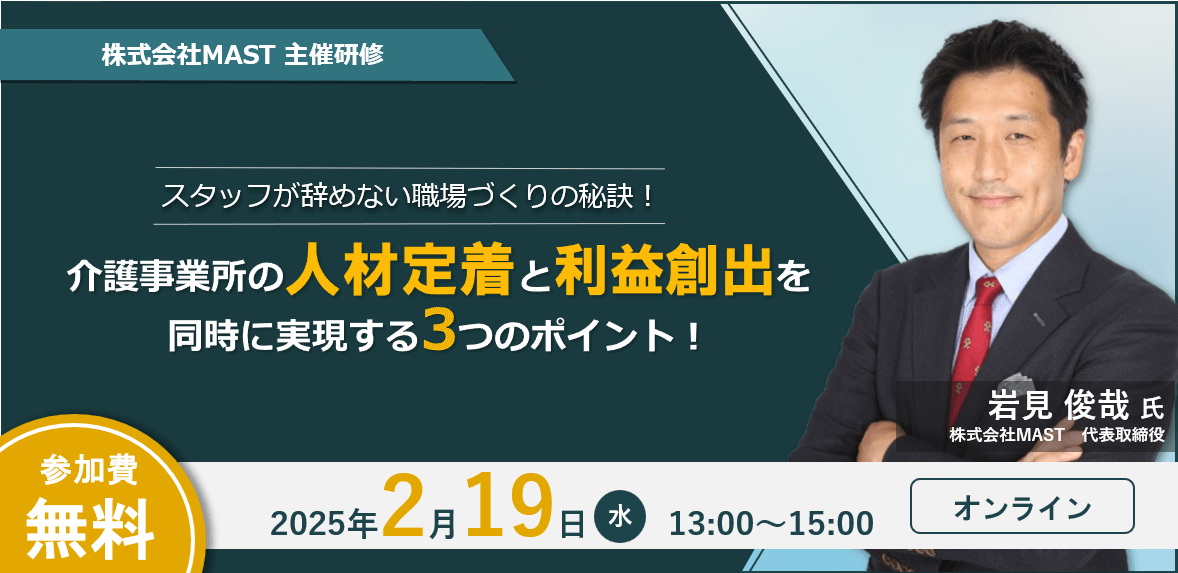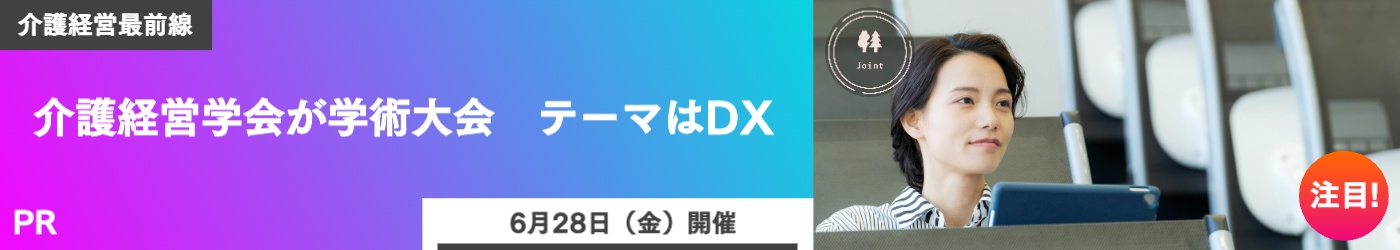注目される医療・介護職のタスクシフト 処遇改善の道筋にもなり得る大きな一歩=天野尊明


前回のコラムで、「的確な未来予測を持って備える」ことの重要性をお伝えしました。今回は、その最たる例である「人口動態から求められているもの」について触れたいと思います。【天野尊明】
まず、国立社会保障・人口問題研究所による直近の人口推計をみると、将来的には65~74歳、75~84歳が減少していきます。それに対して、85歳以上は今後も右肩上がりで増加し続け、2065年頃にはこれら3区分が同数(約1200万人)程度になると見込まれています。
言うまでもなく、誰しも加齢とともに医療・介護ニーズが高まっていくことは避けられません。政府はこうしたことを指して「医療・介護の複合ニーズ」を抱える層の増大という表現をしながら、それに備えた施策を進めています。
介護分野でも例外なく、これまで以上に「医療・介護の複合ニーズ」に応えていかなければならない未来が待っています。介護施設などでは、日常的な範囲の医療的対応が求められていくことは間違いありません。在宅でも例えば、独居高齢者への看取りや認知症のケアが求められるようなケースが増えていくでしょう。
そこで今年度の介護報酬改定では、「医療・介護連携」の基盤づくりが強く推進されることになりました。なかでも踏み込みが大きかったのは、一定要件を満たす協力医療機関の選定が介護施設などに義務付けられたことでしたが、その他にも枚挙にいとまがありません。
この文脈から筆者が注目しているのは、5月31日に政府の規制改革推進会議がまとめた「規制改革推進に関する答申 ~利用者起点の社会変革~」です。
この中では、「医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等」が掲げられました。
具体的には、血糖測定、インスリン注射、蓄尿バック交換・カテーテルとの接続、爪白癬の爪切り、経管栄養チューブからの薬物注入、褥瘡の処置など、現行では看護師らが行っている行為を例にあげ、「関係法令上、介護職員が実施可能な行為には制限があることから、利用者に必要なケアを適時に提供できない場合があるという点で、利用者の不利益となっている」と指摘。そのうえで、
◯ 介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、医行為ではないと考えられる範囲を更に整理すること
◯ 一定の要件の下、介護職員が実施可能と考えられる行為の明確化について、その可否を含めて検討すること
などを求めています。長年膠着していたこの問題を前進させる大きな一歩と言えるでしょう。
上記の介護職員による実施が制限されている行為には、場合によって家族が行うようなものも含まれます。こうした規制を取り払うことは、利用者が抱える日常的な「医療・介護の複合ニーズ」に応えるだけでなく、効果的かつ効率的な形で医療・介護の多職種連携を促し、限られたマンパワーを最大化する土壌づくりにもつながります。
そして、それを担う専門性の高いスタッフについて、より高い評価をもって更なる処遇改善の道筋をつくっていくことも、医療・介護連携のもうひとつのテーマと考えています。
さて、今回のコラムでは、人口動態という物差しから制度の見直しが図られた実例をご紹介しました。
今後のことを言えば、例えばケアマネジャーの方々に対し、医療・介護連携のかけ橋となることが一層強く求められていくことは明らかで、そのために、利用者と現場の双方に必要となるメニューを揃えていかなければなりません。
正しい予測をもって声を届けていくことで、少しずつでも、必ず未来は変えられます。今後も一層活発な議論が交わされることを願ってやみません。