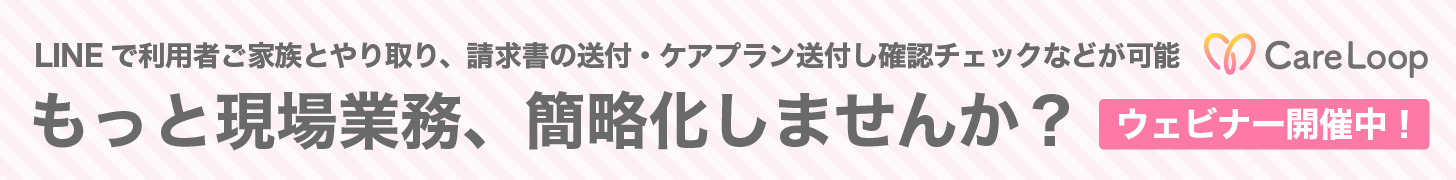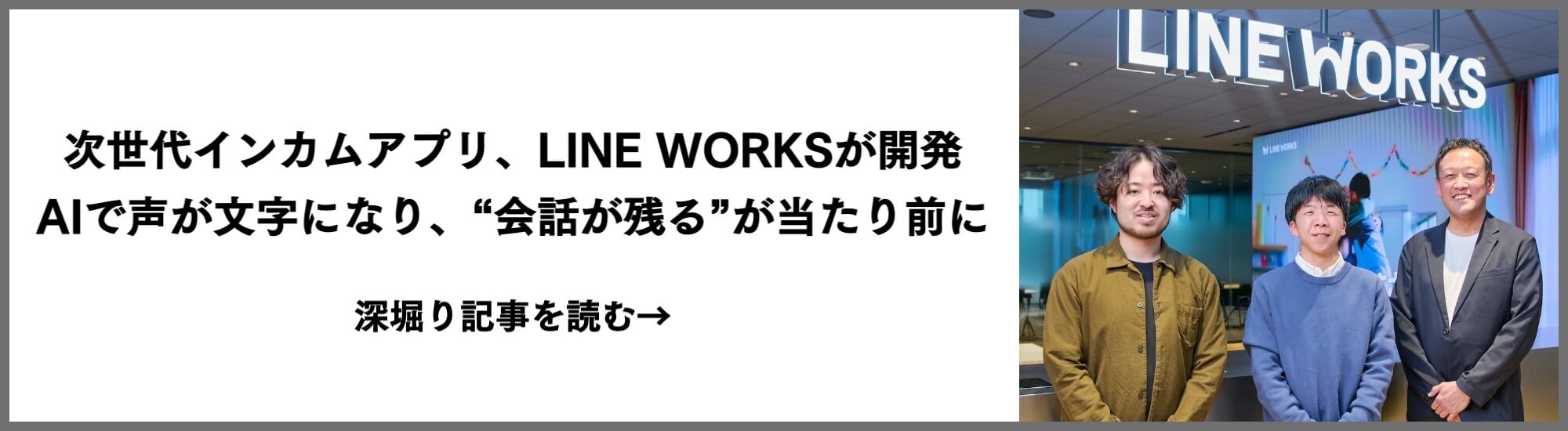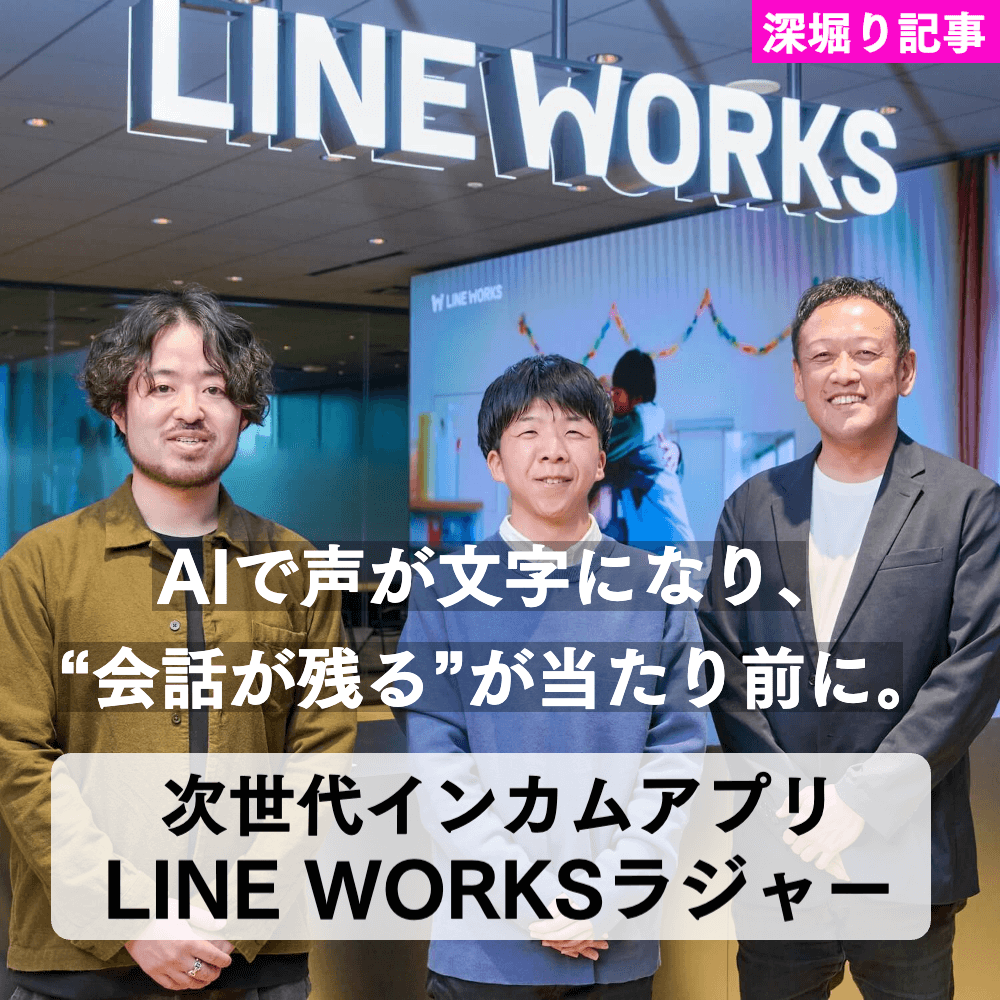【足立圭司】介護現場の生産性向上、カギを握る伴走支援者の役割 2040年へ体制構築が急務


2040年に向けた介護サービス提供体制のあり方を議論してきた厚生労働省の検討会が、4月10日に中間とりまとめを公表しました。【足立圭司】
この中間とりまとめでは、高齢化や人口減少が進展する中で、地域包括ケアシステムを深化させ、持続可能な介護サービス提供体制を構築するための方向性が示されています。
本稿では、中間とりまとめの中から、介護現場の生産性向上に焦点を当て、その普及における伴走支援者の重要性、および今後の展望について述べたいと思います。
◆ 伴走支援者の重要性
中間とりまとめでは、介護現場の生産性向上に向けて、テクノロジーの活用や介護助手などへのタスクシフト/シェアの推進が挙げられています。
しかし、テクノロジーの導入や業務の見直しは、介護現場にとって大きな変革を伴い、不安や抵抗感が生じることも少なくありません。そこで、介護現場を支援し、生産性向上の取り組みを円滑に進める伴走支援者の存在が重要となります。
近年、「伴走支援」という言葉は、介護分野に限らず、様々な場面で見聞きするようになりました。既に多くの都道府県に開設されている生産性向上総合相談センター(ワンストップ窓口)では、地域のベンチマークとなる介護事業所を養成するために、コンサルタントなどの専門家がモデル事業所を伴走的に支援する取り組みが実施されています。
しかしその一方で、多くのワンストップ窓口からは、伴走支援者がいない、または足りないという声が挙がっており、伴走支援体制の確立が急務となっています。このため、「伴走支援者」の役割や具体的な支援手法について議論したうえで、担い手を養成する仕組みの構築が必要と考えられます。
例えば、介護現場のテクノロジー導入において、導入前の計画策定から導入後の効果測定まで、一連のプロセスを支援することが考えられます。具体的には、支援者が介護現場で組成されるプロジェクトチームや委員会とともに、 第一人称で現場課題を分析し、最適なテクノロジーを選定する支援に加え、導入計画の作成、職員への研修、導入後の効果測定、改善提案など、多岐にわたる支援が想定されます。
◆ ワンストップ窓口に仕組み構築を
中間とりまとめでは、都道府県のワンストップ窓口において、介護事業所へのテクノロジーの試用貸出しや研修会・セミナーなどを通じ、テクノロジー導入への不安を解消し、その普及を図るべきであるとされています。
筆者はこれらの取り組みに加え、このワンストップ窓口に、伴走支援者を養成する仕組みを構築することが急務であると考えています。そのためには、先述のようにまずは「伴走支援者」のあり方について丁寧に検討し、 各自治体に向けて発信する必要があるのではないでしょうか。
2040年に向け、介護現場の生産性向上は避けては通れない重要な課題です。伴走支援者は欠かせない存在であり、その確保と育成は急務と言えます。
本稿で述べた伴走支援者の役割や手法に関する議論の必要性が、今後の介護現場の生産性向上への貢献につながれば幸いです。